
|
1.重要伝統的建造物群保存地区とは?
|
||||||||||||||
| 「重要伝統的建造物群保存地区」とは市町村の「伝統的建造物群保存地区」の中で、国がより重要度が高いものとして判断し、補助によって保存整備が行われる地区のことを言います。伝統的 建 築 物 ではなく、伝統的 建 造 物 群 と言っているところがミソで、建築だけが対象なのではなく、構造物や環境などが優れているものも対象地区として実際に選定されています。
この「伝統的建造物群保存地区」は昭和50年の文化財保護法の改正で制度化されたもので、それ自体は「法律的に景観を規制している地区」のことですが、それが国の選定によって「重要伝統的建造物群保存地区」となると、文化財としてより規制が厳しくなるとともに、保存活動に対して国からの補助が受けられるようになります。実質的には、様々なメディアによる宣伝効果により観光入り込みも大幅にアップすると言ってよいでしょう。 「重要伝統的建造物群保存地区」は文化庁で毎年行われる文化審議会によって選定されています。一番最近のものですと、昨年10月に行われた文化審議会によって、「重要伝統的建造物群保存地区」がそれまでの53市町村58地区から、新たに2地区追加されて54市町村60地区となりました。新たに造りあげることが困難な歴史あるものを保存する地なのに、何で後からどんどん追加されるのかと疑問に思われる方も多いかと思います。ちなみに「重要伝統的建造物群保存地区」の選定基準には大きく3つあり、 1.伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの。例1 2.伝統的建造物群や地割がよく旧態を保持してるもの。例2 3.伝統的建造物群やその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの。例3 が挙げられます。つまり、単に歴史ある古いものが対象になるということではなく、修景活動などによって新たに創出された優れた歴史景観をもつ地区も対象になると言うことを意味しています。 点・建築としては歴史的に深い意味のあるものであっても、それが面・地域としてまとまりのあるものでなければ、この「重要伝統的建造物群保存地区」として選定されることはありません。そう考えると、歴史的に意味のある建築や風土に根ざした構造物というものは日本各地にまだまだたくさんあります。では、それらの財産をどのように保存し、つなげて「伝統的建造物群」を作って行くかが一番重要となります。 |
||||||||||||||
|
2.重要伝統的建造物群保存地区の実際
|
||||||||||||||
| では、実際にはどのような地区が伝建地区に選定されているのでしょうか。右には現在選定されている伝建地区のリストを挙げていますが、分類としては、商家町、港町、武家町、山村集落、宿場町などのものが多く選定されているようです。各分類と該当件数についてグラフにまとめています。右に全国の分布図を載せていますが、分布としては、西日本、特に、歴史が色濃く残る近畿・中国・九州地方に多く分布しています。地区の規模としては大きなものから小さなものまで幅広く、現在のところ、長野県南木曾町の妻籠宿が1245.40haと最大で、京都市の祇園新橋が1.4haで最小となっており、39.83haが平均となっています。また、各年度毎の選定件数をグラフにしますと、右のようになります。 次に、各選定基準毎の該当数としては、現在の60件中約半数の29件が選定基準2.「伝統的建造物群や地割がよく旧態を保持しているもの」に該当するとして選定されており、ついで選定基準1.「伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの」が17件、選定基準3.「伝統的建造物群やその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの」が14件となっています。しかし、最近5年間では13件中、選定基準1.と3.が5件ずつと大半を占めている。つまり、最近では、既存の伝統的建造物群にプラスして修景活動を行い、規模を拡大させてきたような地区も審査の対象となっており、伝建地区の仲間入りを果たしています。 |
 |
|||||||||||||
| 伝建地区リスト | 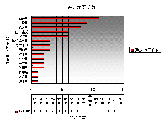 |
|||||||||||||
| 分類と該当件数 | ||||||||||||||
 |
||||||||||||||
| 選定地区の分布 | 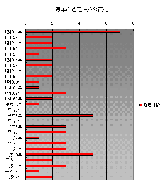 |
|||||||||||||
|
年度毎の選定件数
|
||||||||||||||
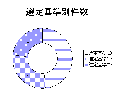 |
||||||||||||||
| 各選定基準毎の該当数 | ||||||||||||||
|
3.重要伝統的建造物群保存地区の事例
|
||||||||||||||
| 【概 要】 今回、伝建地区の一事例として、福島県下郷町の大内宿を調査しました。 大内宿は伝建地区の選定が始まった昭和51年に選定基準3.に該当するとして伝建地区に選定されています。分類は宿場町となっており、会津若松と今市・日光を結ぶ下野街道沿いにもうけられた宿場町で現在、茅葺きの集落がひっそりとたたずんいます。選定面積は11.3haと規模的にはそれほど大きなものではありませんが、選定から20数年、今では全国から多くの観光客が訪れています。調査当日も近県をはじめとする各地から観光客が訪れていました。 【名 物】 高遠そば(ねぎそば)、栃餅、唐辛子、民芸品など 【行 事】 高倉神社半夏祭り(7/2)雪祭り(2月) 【関連事業】 ウォーキングトレイル事業、アダプトロード事業 【見どころ】 茅葺き集落・未だに生活に密着している水路・高倉神社 【課 題】 施設の修繕、アクセスの多様化、散策路の案内表示など 【感 想】 住民の暖かさが印象的でした(方言や質問に対する回答など)。現地は冬に雪が深い地域であるため、対策はどのようになっているのでしょうか。また、民芸品のおみやげ物が印象的でした。お手玉やがんじき、しもつかれ(大根下ろし器)ありました。 【アクセス】 車 電車 |
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
|
参考資料
|
||||||||||||||
| 下郷町観光名所 http://www.akina.ne.jp/~yottaka/Shimogo_town/Shimogo.html YAHOO!トラベル−大内宿 文化庁文化財選集 下郷観光チャンネル 高原の中の茅葺き屋根の宿場町・大内宿 |
||||||||||||||
![]()
編集・発行 まちネタ研究室
mail to matineta@ssss.jp
Copyright(c)2002 MATINETA lab. All Rights Reserved